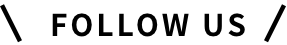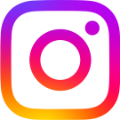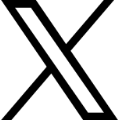おかしなくらいおかし好きおかしなひとたち【2025年】5月10日「黒糖の日」 沖縄県の離島でのみ作られる『沖縄黒糖』 受け継がれていくバトン その③
おかしなくらいおかし好きおかしなひとたち【2025年】5月10日「黒糖の日」 沖縄県の離島でのみ作られる『沖縄黒糖』 受け継がれていくバトン その③
【2025年】5月10日「黒糖の日」 沖縄県の離島でのみ作られる『沖縄黒糖』 受け継がれていくバトン その③
 〜黒砂糖協同組合やJAおきなわの取り組み〜
〜黒砂糖協同組合やJAおきなわの取り組み〜
沖縄黒糖を生産する離島8島を統括する沖縄県黒砂糖協同組合。工場作業員の人手不足や農家の後継者問題など多くの課題を抱えつつも、沖縄黒糖の文化の継承に努力を重ねています。その現状について次長の宇良勇さんからお話を伺いました。またさとうきびをはじめとした農産物の生産から製糖工場の運営、販路拡大などを担うJAおきなわ・マーケティング戦略室の渡久地志麿さんからは、組合との役割の違いや取り組みなどについてお話を伺いました。沖縄現地からの、独占レポートです。

JAおきなわでの取材。左手前から渡久地志麿さん、黒糖の卸販売を行う食品商社の方々、右側に春日井製菓の研究開発メンバー
ストーリーを含めた沖縄黒糖の魅力を積極的に発信していきます。
(沖縄県黒砂糖工業会・沖縄県黒砂糖協同組合 次長 宇良勇さん)
―今期は豊作だったようですね
はい。3年ぶりですね。黒糖の生産量が現時点で9000トンを超えています。台風の襲来が少なかったことと、さとうきびの栽培面積の安定、病害虫防除技術の向上によるものだと思います。品質も良いものができました。温暖化で本土の農作物は大きな影響が出ているようですが、逆に沖縄は台風の襲来が減っています。もちろんさとうきびは台風に強い植物ですが、植え付け時期などに雨が続くと作業が遅れて収穫期のずれにも繋がるので、あまり良いことはないんです。
―働き方改革の影響で、どの工場も人材確保に苦労されたようでしたが
さとうきびの収穫量が増えても、製糖作業を担う人がいなければ、黒糖は作れません。今期から3交代にしなければならず、単純に今までの1.5倍の人が必要になりました。また、今期のように豊作となると操業期間が延び、派遣労働者の確保に苦労していますが、何とかやり切った感はあります。

西表糖業でさとうきびの前処理を行う作業員
―日本人の季節工が減った理由は?
黒糖製糖は概ね4カ月間(※)24時間操業します。働き方改革の影響により勤務時間が減ったことで収入も減少しています。従来はこの短期間にまとまったお金を稼ぐために、北海道、東北、四国などから多くの季節工の方が来ていたのですが、その魅力がなくなってしまいました。季節工だけでなく、工場の職員不足はさらに深刻です。離島には中学校までしかなく、高校進学のために島を離れると、なかなか島には戻ってきません。全国的な人手不足の中、沖縄県の離島にある黒糖工場の最大の課題は、人員の確保と技術の継承です。もう待ったなしの状況です。
※さとうきびの収穫期は12月~3月の4カ月
―解決方法としてどのようなことが考えられますか?
3つあると考えています。
まずは黒糖を使った商品を、皆さんのようなメーカーにどんどん開発してもらって、利用促進してもらうこと。これに尽きると思います。消費量が増えれば、産業も活性化して人も集まってきますから。
もう一つは、住んでみたいと思ってもらえるように、島そのものの魅力を知ってもらうことです。実際に島に戻ってきた方や移住してきた方に、島の景色や生活など、島そのものの魅力を広く伝えてもらうのも重要だと思っています。
最後は、住居問題の解決です。季節工向きの宿舎は完備していますが、職員の宿舎がありません。沖縄は意外と住環境が厳しく、特に石垣島や宮古島などは、リゾート開発が進み、ホテルが次々と建てられているため、地価も上がり、家賃も上がる。資材コストの上昇や職人不足で、新たに建てるにしても価格が高くなります。この問題は行政に関わることになりますが。
―畑の後継者問題は?
確かに放棄された畑もありますが、島の中で別の農家が引き継いでいるケースが多いです。皆さん真面目ですし、都会に比べて相互扶助の精神がまだまだ宿っています。
特に波照間島には、昔ながらの「ユイマール(相互扶助)」という習慣が色濃く残っています。沖縄の方言で、ゆい(結い)とまーる(順番)を組み合わせた言葉で、農作業や家の建築、冠婚葬祭などを島民で協力して行っており、さとうきび畑に関しても、4ヶ月間の収穫期に全農家で順番に島内すべての畑の収穫作業を行っています。農家の戸数は減っていますが、生産量は維持できている理由です。
「ユイマール」について 波照間製糖管理部・西村正太さん談
「さとうきびは収穫した瞬間から劣化が始まります。そのため鮮度の良い原料を搬入するためには農家と工場との連携が重要です。『今日はどの農家の畑からどれだけさとうきびを受け入れるか』かという情報を共有することで搬入量を調整し、刈り置き期間を短縮することで劣化を防ぎます。ただ、農家は個人事業主になるので、まとめるのはなかなか難しい。そういう点で昔からの『ユイマール』が重要になるわけです。最近、工場に県内外から4人の移住者を迎えました。波照間島は石垣島からのアクセスは決して良いとは言えませんが、その分海は圧倒的に美しいですし、かえって希少価値があるのかもしれません。とはいえ、作業の機械化と省人化は避けて通れません。特に人手を要する箱詰め作業に代わる自動充填機をはじめ、荷崩れ防止のラップ包装機など、他の離島ではやっていないことも、試行錯誤しながら徐々に導入しています。抱えている課題はどの工場も同じですから、全工場担当者が集まって勉強会を開いたり、機械化などの横展開につながると嬉しいです。8つの離島全体が一つの『沖縄黒糖』のユニットですから」
―沖縄黒糖の認知度アップのためにおもしろい取り組みを始めたそうですね
2025年2月に、沖縄県出身の5組の芸人による『沖縄黒糖ネタバトル2025』というお笑いイベントを開催しました。昨年の東京に続き、今回が初の地元開催です。沖縄出身の若手芸人5組が出場。「沖縄黒糖」というネタ縛りでネタを披露してもらいました。このイベントには2つの狙いがあります。一つは、もちろん若い世代に沖縄黒糖を身近に感じてもらうことと、もう一つは地元出身の芸人自体が沖縄黒糖のストーリーを理解する機会になることです。この先、沖縄黒糖ネタが次に繋がっていく可能性もありますから。沖縄黒糖のおいしさを知ってもらうためには、ダイレクトに味を訴えるだけではなく、背景にあるストーリーも知ってもらうことが大切だと考えています。
今年7月には、沖縄本島に新たなテーマパークが開業します。まだまだ手探り状態ですが、飲食店をはじめ、土産品などで沖縄黒糖を使った商品を展開してもらえれば、国内外の方々に知ってもらえるチャンスです。まだ具体的な話はありませんが、我々は商品を作ることはできませんので、沖縄黒糖を使った新たなコラボ商品の開発を、メーカーさんに進めてもらえたら嬉しいですね。

「沖縄黒糖ネタバトル」のチラシ

沖縄県黒砂糖協同組合の入口に展示されている各島の黒糖商品
農家を全面的にサポート。PR活動も本格的に始めています。
(JAおきなわ農業振興本部マーケティング戦略室 渡久地志麿さん)

―JAおきなわの役割を教えてください。
JAは農家主体で始まった組織です。沖縄県では、さとうきびは県の基幹作物ですから、特に力を入れており、「さとうきび振興部」と「マーケティング戦略室」の2つの部署が連携して生産振興と販売強化に取り組んでいます。「さとうきび振興部」は、工場運営がメインのグループと、さとうきびの栽培に関するグループの2つに分かれています。「マーケティング戦略室」は、沖縄黒糖の販売に特化した部署です。
工場運営に関しては、現在、西表島、波照間島、多良間島以外の5島をJAが担当しており、現地では生産~製造を主に行っています。さとうきびの栽培に関しては、肥料や農薬の販売や、個人で取得するには高額なハーベスターをJAが導入支援し、農家に委託するなどの業務を担当しています。

波照間島のハーベスター。収穫しながら裁断まで可能
―「さとうきび振興部」では生産調整なども行っているとか?
私も以前は「さとうきび振興部」で機械導入などを担当していました。たくさん作ってたくさん売れば良いというわけではないんです。さとうきびが豊作であれば、製糖作業の時期が長くなると翌年の準備が遅れ、収穫量に影響を及ぼし、需給バランスが崩れてしまいます。安定生産、安定供給があるべき姿なんです。難しいところなんですが。もちろん需要が増えても、それに対応できる状況を作っておくことがベストですが、農家も減っていますので、安定生産を行うのが難しい状況です。
―放棄畑もJAが引き継いでいるのでしょうか?
少し前には、不作が続いていたこともあって、生産量維持のために工場運営で畑をやる場合もありました。ただ、最近は比較的若い、といっても4、50代ですが、農地を広げたいという人が増えてきて、いい流れになっています。

― 黒砂糖協同組合とも連携されているとか
たとえば国や県、市町村など行政への依頼などに関しては、現場の声を集約して協同組合が前面に立っています。そのバックアップにJAグループも協力しています。勤務時間体制が今期から大きく変わったこともあり、まさに過渡期を迎えています。今後のことは黒砂糖協同組合と肩を組んでよりよい体制づくりに注力していきたいと考えています。
他にもJAのサポートとしては、たとえば病害虫が発生した際、国や自治体へ補助金を申請し、農家さんに安価で薬剤や肥料を供給できるようにすることなどです。さとうきびに関しては、他の作物に比べるとかなり手厚いサポート体制が整っています。やはり関係人口が多いですし、国土防衛の意味合いも持っている重要な産業ですから。
―JAとしての新たな取り組みも精力的に行っているそうですね
「JAおきなわ黒糖5つ星プロジェクト」を2020年に立ち上げました。JA管轄の5つの島で生産される黒糖の魅力を伝え、販路の拡大が目的です。黒糖の栄養面をアピールするために、オリジナル黒糖レシピの提案と発信。「JAおきなわ黒糖防災缶」のような、新たな商品の開発。企業とタイアップして販売促進やイベントなどの実施など、単に原料を販売するだけでなく、マーケティング戦略室が立ち上がったことで、PRにも力を入れられるようになりました。

JAおきなわが発信しているWEBサイト
―今後の運営について教えてください
昨年の秋に、JA全農とメーカーが企画する「ニッポンエールプロジェクト協議会」という産地応援の取組に、沖縄黒糖を取り上げてもらいました。全国規模の大手メーカーに、黒糖を使った新商品を6アイテム作ってもらい、広く知ってもらうことができました。
ニッポンエールプロジェクト 沖縄県産黒糖
今後もこうしたPR企画への参加はもちろんですが、春日井製菓さんのように、予防医学の面から黒糖の魅力に迫るなど、より具体的な研究結果に基づいた健康面からのアプローチにより、黒糖の新たな魅力も発信していくことが、一層重要になっていくと考えています。
春日井製菓では今後も沖縄黒糖の機能性についての研究や商品開発、そして情報発信を続けていきます。

春日井製菓商品開発部のみなさん
そのほかの沖縄黒糖記事はこちら。
眠っている黒糖の知られざる底力
https://www.kasugai.co.jp/okashifreak/kokutoupower01/
https://www.kasugai.co.jp/okashifreak/kokutoupower02/
 ライター・ましもさとこ
ライター・ましもさとこ
一日一餡を公言するアンコ好きライター。
甘いも、しょっぱいも、熱いも、冷たいも…どんなお菓子も人間もなんでもござれ!
2児の母でもあり、自宅にはお菓子専用ストッカーを設置。
通称「グミ也」と呼ばれるグミ好きの次男のために箱買いしている「つぶグミ」(特につぶグミプレミアムがお気に入り)が占拠している。