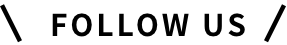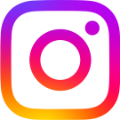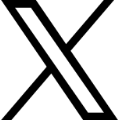おかしなくらいおかし好きおかしなひとたち【2025年】5月10日「黒糖の日」 沖縄県の離島でのみ作られる『沖縄黒糖』 受け継がれていくバトン その②
おかしなくらいおかし好きおかしなひとたち【2025年】5月10日「黒糖の日」 沖縄県の離島でのみ作られる『沖縄黒糖』 受け継がれていくバトン その②
【2025年】5月10日「黒糖の日」 沖縄県の離島でのみ作られる『沖縄黒糖』 受け継がれていくバトン その②
 〜小浜島〜
〜小浜島〜
2001年に放送されたNHKの朝ドラ「ちゅらさん」の舞台となり、一躍その名が知られるようになった小浜島。石垣島から高速船に揺られること30分。人口748人の、のんびりとした小さな島です。島内に流れるのは、ゆったりとした島時間。一面のさとうきび畑にまっすぐ伸びるシュガーロードは、1kmも続きます。一度見たら忘れられない美しい海岸線など、多くの旅人の心を魅了し続けている島です。
そんな小浜島の主要産業である黒糖製造を、一手に担うのがJAおきなわ 八重山地区営農振興センター 小浜製糖工場。さとうきび栽培や黒糖製造について話を伺うとともに、実際に移住してさとうきびを作る農家さんにも会いに行って来ました。

小浜港にある島内地図

『ちゅらさん』の生家として使われた「こはぐら荘」。民家のため中には入れないが、看板は撮影当時のまま残されている
JA直営の製糖工場。販売方法や製法の違いにクローズアップ
波照間島、西表島、多良間島の製糖工場は民間会社が経営している一方、小浜島をはじめとしたほかの5島はJAおきなわが管轄。その違いとは?
「JAでは、各島の工場は製造業務が主となり、販売業務については沖縄本島で5島を一括管理する販売部署が担っているのが大きな違いです。そのため、島内での販売は島民やお土産用などごくわずかです」
と小浜製糖工場専任部長の嘉数勲さん。
小浜島は、以前は小さな民間工場がいくつかあったものの、後継者がいなくなったことで経営が厳しくなり、JAが引き継いだそう。

小浜製糖工場の入り口。小浜港から徒歩で7分ほど
島内のさとうきび農家数は全58戸で、前年より7戸増加。黒糖生産量はおよそ512トンで、前期に比べて約1.6倍と、順調な年だった。ただし西表島と同様、小浜島でも季節工の募集には苦労。
最終的には34名採用し、日本人22名、残り12名は全員インドネシア人だった。特にインドネシア人のみを募集したわけではないが、“できれば”インドネシアからとの文言を添えた結果だ。

「宗教上の食事の問題が大きいからです。寮で提供する料理に手間がかからないようにするためにも、一つの国の方がありがたいので」
と嘉数さん。
「黒糖の製造工程に関しては、他の工場とほぼ変わりません。唯一の違いは、蒸発濃縮装置です。西表島は横向きですが、小浜島では縦向きの装置です。波照間島ではオープンパンと言われるものを使っています。オープンパンだと乾燥が早いので出来上がりが少し硬めです。小浜島は柔らかめで口の中でホロリとほどける感じになるのが特徴です」。

工場に隣接する広大なさとうきび集積所

波照間、西表と同じく、小浜も同じ形の「ジュースヒーター」と呼ばれるもので、さとうきびの汁を加熱し、非糖分を凝固する

エバオレーターと呼ばれる濃縮装置。太い管が垂直に立っている
小浜島の土壌はさとうきび栽培に最適
およそ9割を手刈りでさとうきびを収穫する波照間島に比べて、小浜島は手刈りが4割で、機械刈り(ハーベスター)が6割。さらに、苗の植え付けも、スマート農業の一環として、『ビレットプランター』と呼ばれる機械を導入している。
「小浜島の土壌の大半は、『国頭マージ』と呼ばれる赤土で、保水性や通気性に優れており、さとうきび栽培に向いています。反面、肥料の“もち”が良くないため、より多くの肥料が必要になります。ハーベスターで刈ってしまうと、葉や根もすべて収穫してしまい農地への還元ができず地力増進(畑の質を高めること)や循環型農業の妨げとなることが課題です」
と語るのは、同じく小浜製糖工場の北村晃子さん。北村さんは、かつて八重山地方に旅行に来た際、さとうきび刈りのボランティアに参加。その時に知り合った夫の浩吉さんと共に、小浜島に惹かれて本州からやってきた移住組だ。現在、製糖工場で働きながら、浩吉さんと共にさとうきびを栽培している。
「小浜島には、人と人とのつながりをとても大切にする文化が根付いています。その温かな関係に惹かれたのも移住の理由の一つでした。ただ、さとうきび農家もしかりですが、急速な高齢化に、島の文化を守り伝えていくことに不安を感じています」(北村さん)
「小浜島のさとうきび農家で、39歳以下は全体の1割未満です。高齢化が進む一方ですが、黒糖文化は守っていかなければなりません。そのためには春日井製菓さんのようなメーカーに沖縄黒糖をたくさん使ってもらうこと、消費者の方に黒糖の良さを知ってもらうこと。そして作り手である農家は、自分たちが作ったさとうきびから作られる沖縄黒糖が、どう使われるかを知ることこそが、黒糖を作り続けていくモチベーションになります。黒糖文化を次の世代に伝えていくために大切なことだと思っています」(嘉数さん)
嘉数さんの言葉に、春日井製菓商品開発部の本田寛幸さんはこう答えた。
「400年の歴史がある沖縄黒糖。食べ続けられているのには理由があるのでは?と研究を続けています。世界には長寿の地域が5カ所あって、沖縄もその一つです。研究を進めていく中で、実は黒糖に含まれているポリフェノールが健康長寿に関係しているのではないかということがわかり、さらに研究を進めています。より具体的に効果が明らかになれば、チョコレートのように『黒糖のポリフェノールブーム』を起こしていけたらと思っています」

小浜島では小型と中型の2台のハーベスターを使っている
さとうきび栽培に魅了され東京から移住
さとうきび収穫の最盛期。4mほどの高さがあろうかというさとうきびを、もくもくと手刈りしていたのは、東京から小浜島に移住して6年目を迎えるという重信里佳さん。ご主人と共に、およ8haの畑でさとうきびを栽培している。

重信里佳さんは、小浜島の人と黒糖に惚れ込んで移住した
里佳さんは、12年間会社員として勤務後、自分の手で何かを生み出したいと考えていた。その時たまたまさとうきび畑を譲ってくれる人がいることを知り、小浜島へ。ご主人とはこの島で出会った。ご主人のお父様もさとうきびを作っていたが、自身は未経験。
「基本的な作り方は役場の人に教えてもらいました。そこからは自己流ですね」
と笑う里佳さん。さとうきびの価格は糖度が高いほど高価になるため、いかに糖度を上げるかが栽培の最重要課題だと。糖度の高い果物の研究など、努力に努力を重ねてきたという。
「植え付けの時はどんなさとうきびが育つか、毎回ワクワクしますし、年末の収穫期は、無心で刈り取る。この時間が心を浄化してくれる。これが心地良いんです。今年は作付け面積を1.5倍に広げました。収穫量も増える分大変ですが、収入も増えると期待しています」
収穫期になると、東京の友人をはじめ、前職の上司も刈り取りの手伝いに来てくれるそうだ。
「私が黒糖を配ったことで、食べるようになったという友人も増えており、刈り取りの手伝いに来てくれるなど、高い関心を持ってくれるようになったことを感じています。もっとがんばっておいしいさとうきびを作らなければと気合も入ります」
そう語って、軽やかな足取りで再び畑へと戻って行った。

東京出身の重信里佳さん

重信さんの畑。積み上げられていた手刈りのさとうきび
そのほかの沖縄黒糖記事はこちら。

 ライター:ましもさとこ
ライター:ましもさとこ
一日一餡を公言するアンコ好きライター。
甘いも、しょっぱいも、熱いも、冷たいも…どんなお菓子も人間もなんでもござれ!
2児の母でもあり、自宅にはお菓子専用ストッカーを設置。
通称「グミ也」と呼ばれるグミ好きの次男のために箱買いしている「つぶグミ」(特につぶグミプレミアムがお気に入り)が占拠している。