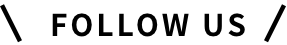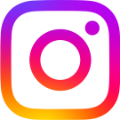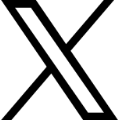おかしなくらいおかし好きおかしなひとたち【2025年】5月10日「黒糖の日」沖縄県の離島でのみ作られる『沖縄黒糖』 受け継がれていくバトン その①
おかしなくらいおかし好きおかしなひとたち【2025年】5月10日「黒糖の日」沖縄県の離島でのみ作られる『沖縄黒糖』 受け継がれていくバトン その①
【2025年】5月10日「黒糖の日」沖縄県の離島でのみ作られる『沖縄黒糖』 受け継がれていくバトン その①
 〜西表糖業のその後〜
〜西表糖業のその後〜
1980年に春日井製菓が発売してから45周年。こっくりとした深みがあるのにクセがなく、ふと食べたくなる黒あめ。ちょっぴり大きめの粒で、長く舐めていられることも、子どもの頃は嬉しかった…黒あめは、幅広い世代で長く愛され続けている、春日井製菓を代表するキャンディの一つです。
黒あめの原料となっている「沖縄黒糖」は、沖縄県の8つの離島でのみ作られている黒糖のブランド名です。(※1)「今年は3年ぶりの豊作」という嬉しいニュースに足取りも軽やかに、沖縄黒糖の故郷である西表島と小浜島、さらに沖縄県黒砂糖協同組合と離島全体を管轄するJAおきなわも訪問してきました。さとうきび栽培の現状や畑を受け継ぐアトツギや移住者、そして統括する団体の取り組みをご紹介します。
※1 :「沖縄黒糖」は黒糖のブランド名。沖縄県にある8つの離島「伊平屋島、伊江島、粟国島、多良間島、小浜島、西表島、波照間島、与那国島」で、栽培されるさとうきびから作られた黒糖にのみ与えられる名称です。
人手不足はさらに深刻化
島全体が国立公園に指定されている西表島。今期の黒糖生産量は1400トンほどで、8つの離島の中でも3番目に多い。予定以上の量を確保できて、農家たちもホッとしているそう。島内にあるさとうきび農家は全78戸で、全農家の7割ほどを占める。今期も収穫、製糖作業が終了し、出来栄えも上々とのこと。(※製糖工程については、2024年の「黒糖の日」記事をご覧ください)

港に設置された島内マップ。日本の離島の中で、沖縄本島に次いで2番目に大きい西表島

西表糖業に集められたさとうきび。この量をすべて1日で製糖する
昨季から大きく変わったことと言えば、2024年4月から国の「働き方改革関連法」によって時間外労働の上限が規制され、これまで昼夜2交代で行っていた製糖作業を3交代にしなければならなくなったことだ。
例年さとうきびの収穫は、12月から3月いっぱいまでのわずか4カ月間。さとうきびは特に鮮度が命と言われる生鮮品のため、収穫後、できるだけ早く製糖しなければ質の良い黒糖が作れない。そのため製糖期の工場は24時間のフル稼働となる。3交代になると、その分人手が必要となり、人材の確保に苦労したと語るのは、西表糖業総務部の赤嶺穣さん。
「カンボジアやミャンマー、インドネシアなどアジアの国々から、今期はたくさん来てもらいました。もちろんできるところは機械化も進めていますが、さとうきびを収穫するためのハーベスターを増やせばいいという問題でもないんです。一度の収穫量が増えたら、その分、すぐに製糖しなければならないため、工場で手が回らなくなる。悩ましいところです」

総務部の赤嶺穣さん(左)と曽木規予さん(右)
もう一つは、日本全体の課題でもある後継者問題。製糖工程において、さとうきびの状態を見極めて、温度の上げ具合など職人の目と技が必要になる。沖縄の黒糖文化を守っていくためには、この製糖技術を次の世代へ繋いでいかなければならない。
「たとえば50歳の方は、定年まであと10年あるからじっくり教えていけばいいと思うかもしれませんが、製糖期間はたった4カ月です。しかも回数にしたら残り10回しかありません。ただアトツギの若者や、内地からの移住者なども少しずつですが増えているのは明るい話題です。黒糖産業は離島の基幹産業ですから。やりがいのある仕事だと思いますね」


手作業の工程も多い黒糖製造
島の活性化を担う、期待のアトツギや移住者
製糖工場の視察後は、さとうきび畑へ。現役農家の父と共に、20haのさとうきび畑を大切に守っている友利良太さん。生まれも育ちも西表島。18歳で西表糖業の工場に勤務したのち、20歳の時に実家のさとうきび畑を継いだ。良太さんと父をはじめ、計4人で年間700トンのさとうきびを栽培している。

広大な友利さんのさとうきび畑
「品種改良が進んでいて、随分育てやすくなっています。栽培は天候に左右されますので、台風に強いさとうきびとはいえ、あまりにも多いと害虫被害が出てしまいます。最近の温暖化で害虫が増えているような気がします。ただ、初期段階で対策を打てば株自体の質が良くなっているので、ちゃんと育ってくれます。手をかけた分だけ、いいさとうきびが育つんです。ちゃんと応えてくれる。これが何よりのやりがいですし喜びですね」
友利さんは、真っ黒に日焼けした顔をほころばせた。

一方、西表糖業に勤務して4年目の曽木規予さんは、福岡からの移住者だ。福岡市内のコールセンターで10年間勤めたのち、旅好きが高じて2011年、西表島のリゾートホテルに転職。しかしホテルの経営者が変わったタイミングで、大型免許を取得して、西表島交通の観光バスの運転手へ華麗なる転職を遂げている。

西表島に移住して14年の曽木規予さん
「なぜ?って思いますよね。西表島交通の観光バスの運転手は、観光ガイドも兼ねるんです。それが楽しくて。ところがコロナになってお客さんが激減して、事業は縮小。そこで募集のあった西表糖業に転職しました。いろいろありましたが、西表島を離れようとは思ったことは一度もありません。ここ以上に居心地の良いところはないんじゃないかな」
と曽木さん。島の人に紹介された古民家に、愛猫3匹と住んでいる。島内の移動手段は、中古のバイクだ。快適な通信環境のもと、ひとりで過ごす時は趣味の映画鑑賞を楽しんでいる。福岡に帰省するのは多くても年に1度ほどだそう。
「福岡は、どこに行くにも電車にのらないとダメですし、人が多くて疲れます。島には家から5分圏内にコンビニもないし、夜9時以降、買い物ができないことも、慣れれば何ともないです」
とカラリと笑う。現在、曽木さんはアルバイトの採用や勤怠管理、寮の管理などを担当している。製糖期間が終われば、次の収穫期のために、寮の準備や人材の募集に駆け回る。仕事終わりには、西表島への移住仲間との交流も楽しんでいる。さとうきび畑で働く人をはじめ、観光ガイドやマリンスポーツのインストラクター、料理屋でのアルバイトなど、仕事も様々だ。旅行で来て、そのまま居着いて、農家の人と結婚した女性もいるそう。曽木さんの周りでは、若い人の移住が増えている感覚とのこと。
それでも製糖工場での採用に苦労するのはなぜ?
「離島で働きたいという人は、沖縄らしい自然に関わる仕事を求めて来ます。その点、観光業やマリンスポーツはもちろん、最近では農業を始める人も。問題は当社のような工場内での仕事です。沖縄の離島でなくても(できる仕事)…となりますからね。
ただ西表島では住居の問題が大きいのです。世界遺産の西表島ならではだと思いますが、新しい家が簡単に建てられないですし、空き家が出てもすぐに埋まってしまう。ベストは働きながら地元の人と仲良くなって、空き家情報をもらうことです。私もこの方法で今の家を見つけましたから。まずは製糖期間に働いて、その間に家探しをして移住する方法もありますよね。その点、製糖工場には個室で快適な寮が完備されていますし、3食付き。3交代になって休みもしっかりありますから島の生活も満喫できます。」

地元の若い女性たちに人気の島内のカフェ
さとうきび農家と製糖工場はワンセット。
「どちらも高齢化が進んでいます。離島経済を支える黒糖産業は、日本の国土防衛にも関わる重要なものとして位置付けられています。(※黒糖産業と国土防衛の関わりについてはこちらの記事をご覧ください)なくすわけにはいかないんです」
と曽木さん。西表島への移住のプロセスから島での生活まで、移住者の目線でありのままを語り、最後にこう締め括った。
「まずは来て、見てほしいですね。愉快な島の仲間たちがお迎えしますよ!」
そのほかの沖縄黒糖記事はこちら。
眠っている黒糖の知られざる底力
https://www.kasugai.co.jp/okashifreak/kokutoupower01/
https://www.kasugai.co.jp/okashifreak/kokutoupower02/
 ライターましもさとこ
ライターましもさとこ
一日一餡を公言するアンコ好きライター。
甘いも、しょっぱいも、熱いも、冷たいも…どんなお菓子も人間もなんでもござれ!
2児の母でもあり、自宅にはお菓子専用ストッカーを設置。
通称「グミ也」と呼ばれるグミ好きの次男のために箱買いしている「つぶグミ」(特につぶグミプレミアムがお気に入り)が占拠している。